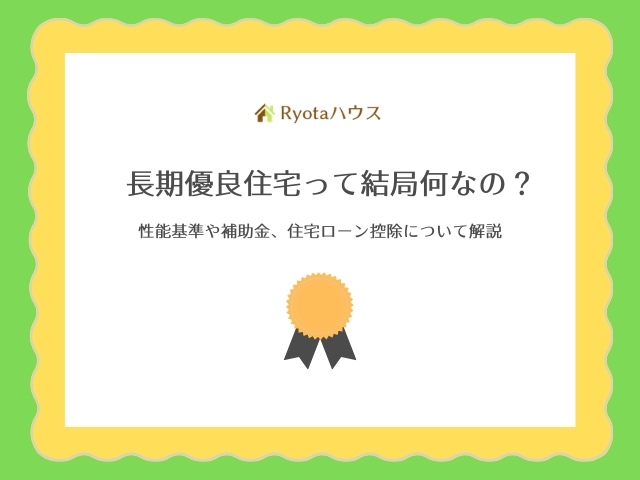
「長期優良住宅とは何なんだろう…。やっぱり適用した方がいいのかな?メリットやデメリットを知りたい。」
そんな疑問にお答えします。
当記事を読めば長期優良住宅についてわかります。
長期優良住宅をやめたRyotaです。メリットはたくさんなんですが、家の価格は上がっちゃうんです。


そもそも長期優良住宅は何なのか…という点からお話しします。
気になる税金控除についてもお話ししますのでお役立てくださいね。
▼家の資金繰りが無料で作れる!▼
-

-
これからマイホーム計画をするあなたへ『家作り計画書』を作るメリット
続きを見る
▼家作りで節約できる内容のまとめ▼
-

-
【家づくりを絶対節約!】Ryotaハウスツリー/比較で節約する情報まとめ
続きを見る
1.長期優良住宅って何?認定基準について
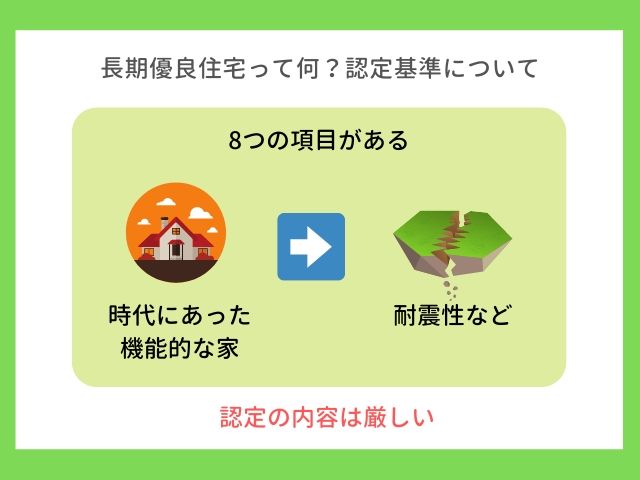
長期優良住宅とは
以下の8つが認定基準です。
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持のしやすさ
- 間取りの変更が簡単
- バリアフリー
- 省エネ性
- 住宅の環境
- 住宅の面積
ざっくりまとめると『時代にあった安全で素敵な家を建てたかどうか』です。


周りの環境への配慮も求められます。
外観がなじんでいるかどうか。維持しやすいかもチェック対象。
これを満たして所管行政庁に届け出を出せば長期優良住宅と認められます。
① 劣化対策

劣化対策の内容
普通の環境で100年ほど構造が使えるかどうかをチェックされます。
チェックするために『床下と小屋裏の点検口設置』『点検しやすい床下の高さ』が基準になります。
とは言え、ほとんどの住宅で点検口は設置されます。構造の方が問題になりますね。
鉄筋の場合はコンクリートの水量・鉄筋のコンクリートかぶりの量が判断基準です。
② 耐震性

大地震にも備えられているか
大地震に対して『損害を軽度にして、また使える家づくり』が求められます。
耐震性のポイント
- 建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しない
- 住宅品確法に定める免震建築物
- 大地震に対する変形を一定にとどめる
- 大地震の時の各階変形度合いを1/100以下(建築基準法レベルの場合は1/75以下)にする
構造を強くする。耐震性を高めなさいねってことです。
ちなみに制震・免震の家ってほとんどないです。基本的には『耐震』で考えましょう。
▼耐震性についてはこちら▼
-

-
耐震等級3の地震に強い家を建ててわかった4つのこと『個人で備える』
続きを見る
③ 維持のしやすさ

家の維持管理がしやすいか
構造は100年持っても、各設備の寿命って短いじゃないですか。
キッチンやお風呂周りは数十年で寿命が来ちゃいますよね…。その時に取り換えが簡単かどうかです。


例えば壁を破壊しなくてもキッチンが交換出来たら嬉しいですよね。そういう措置が取られてるかどうかです。
④ 間取りの変更が簡単
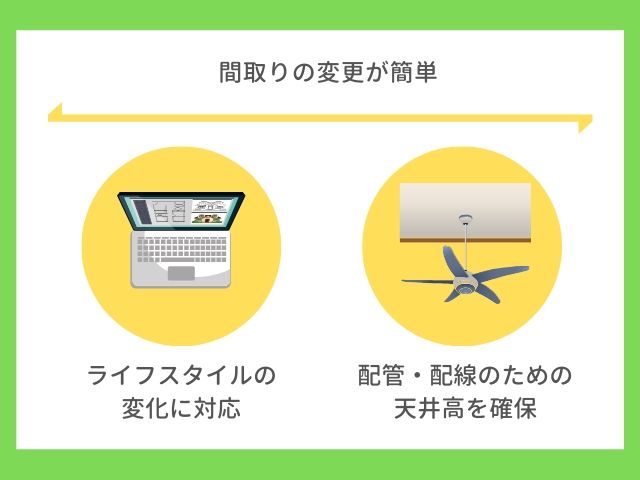
将来性が高いかどうか
難しく言えば『可変性があるかどうか』です。
可変性の例
- 子ども部屋を1部屋・2部屋に分割できる
- トイレが2つあるので家族が増えても対応できる
自由な間取りに便利な天井高も求められます。
⑤ バリアフリー
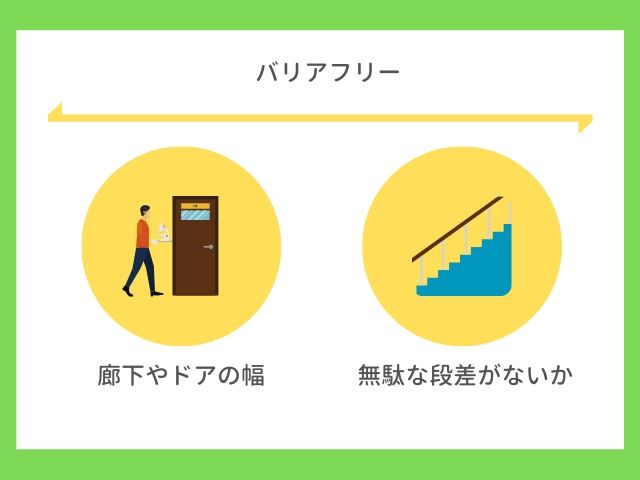
将来、バリアフリーにできる
将来、バリアフリー環境が整えられるかどうかです。
バリアフリーのポイント
- 廊下に必要なスペースがあるか
- 階段の幅、傾斜は無理がないか
- エレベーター設置の広さはあるか
私の妻の家がバリアフリー。基本的に段差がないです。
スキップフロアや小さな段差のあるなしも判断材料になるかもしれませんね。
⑥ 省エネ性
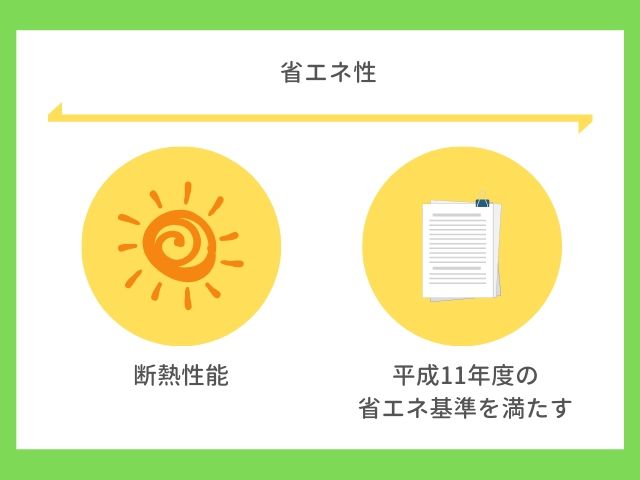
省エネ性があるかどうか
平成11年度の省エネルギー基準を満たしているかどうかです。
断熱性や日射遮蔽性が求められます。家が快適な空間かどうかが見られますね。
この基準が上がっていき低炭素基準やZEH住宅が登場しています。補助金ももらえますね。
⑦ 住宅の環境

家の外観に問題はないか
見た目が悪くないか。周りの人を不快にさせないかチェックされます。


地区計画、景観計画、条例で街並みが決まっている場合も、調和が取れているか見られます。
城下町なら『和風な感じ』が求められるってことですね。
⑧ 住宅の面積

家がそれなりに広いかどうか
住みやすい居住空間確保のため、一定の広さが求められます。
これは認定基準をそのまま引用しますね。
〔戸建て住宅〕
・75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)※戸建て住宅、共同住宅とも、地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし、戸建て住宅55㎡、共同住宅40㎡(いずれも1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。
地域の実情により引上げ・引下げがあります。
自治体によって変わってくるのかなと想像できますね。事前に工務店側と相談しましょう。
長期優良住宅は税金がかなり優遇されます。以下続けて解説していきます。
2.長期優良住宅の税金優遇措置について
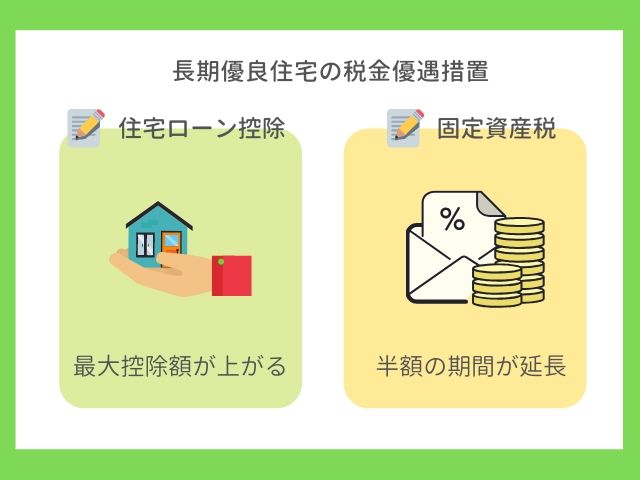
長期優良住宅がお得な理由
以下の4つです。
- 住宅ローン控除が増える
- 投資型減税
- 不動産取得税の軽減
- 固定資産税の軽減
固定資産税と不動産取得税については全員が該当します。
住宅ローンと投資型減税は『控除できない可能性』もありますね。該当しているか確認しましょう。
① 住宅ローン控除が増える
一般住宅の控除対象額は最大4,000万円まで。
長期優良住宅の場合は最大5,000万円まで増額されます。


一般住宅よりも100万円ほど税金がお得になると考えてください。
住宅ローンを4,000万円以上借りた人じゃないと控除額に影響しません。
住宅ローン控除については特集しています。詳しくは以下をどうぞ。
-

-
新築の住宅ローン控除ってどのくらい?気になる控除額・適用条件について
続きを見る
② 投資型減税

長期優良住宅の投資型減税について
住宅ローンを使わずに長期優良住宅・低炭素住宅を建てる場合に税金が控除されます。
投資型減税の内容
- 控除限度額は650万円
- 10%が1年間控除される
- 最大65万円まで控除
控除しきれない場合は翌年の所得税から控除されます。
③ 不動産取得税の軽減

不動産取得税について
家や土地を買った時にかかる税金です。
一般住宅は1,200万円まで控除されます。長期優良住宅の場合、1,300万円まで控除。


※税率は4%なのですが、2021年3月31日の取得までは3%に引き下げられてます。
3,500万円の長期優良住宅新築一戸建てを買い、家の評価額が1,250万とします。
(1,250万-1,300万)×3%なので負担はゼロですね。土地の不動産所得税のみかかる計算になります。
④ 固定資産税の軽減
新築を建てた場合、固定資産税が3年間半額になります。
長期優良住宅の場合5年間半額。2年も延長します。
ただし、これらの内容は一時的なもの。途中で終了することがあります。
国税庁や各種税金ページをチェック。工務店とも現在の状況を聞いて優遇措置が残っているか確認してくださいね。
また、フラット35を好条件で借りやすくなるメリットもあります。
3.長期優良住宅を建てるデメリット
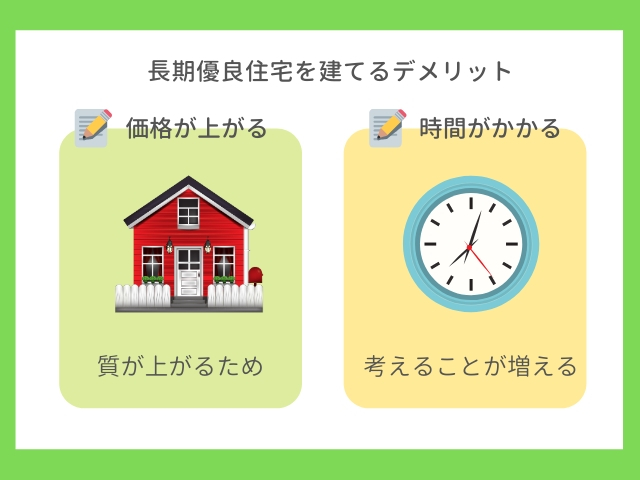
長期優良住宅はデメリットもある
以下の2つです。
- 建てるのに時間やお金がかかる
- 申請にお金がかかる
考えることが増えますよね。家の品質も上がるので価格が上がります。
補助金や控除があったとしても、一般的な住宅よりは高いです…。
① 建てるのに時間やお金がかかる
例えば『耐震性を上げる』だけでも予算は上がりますよね。


当然、構造も長く使える丈夫なものになります。省エネ性を高めるために断熱材性能も良くしないとですよね。
しかも『考える部分が増える』んです。
間取りを考える時間だけでも長くなります。
家を建てる時間が長くなればそれだけアパート代が無駄になりますよね。
② 申請にお金がかかる

長期優良住宅は審査におよそ10万円
申請で10万円ほどかかります。
次世代住宅ポイントなど長期優良住宅が有利になる補助金があります。
でも、逆に損しちゃう可能性が出てくるんです。


耐震性だと『耐震性3相当』って言葉がありますよね。
長期優良住宅の場合は認定されないと補助金や控除が使えません。もったいないです。
長期優良住宅を建てたいあなたへ

吹き抜けのある住宅を建てている最中
一般住宅との差額をおおよそでいいので判断しましょう。
プラス100万で長期優良住宅にできるのなら検討する価値があります。
しかし、プラス300万以上になれば厳しいですよね…。メーカーにより標準機能が違うので価格は調べないとわかりません。
『家作り計画書サービス』を使えば資金繰りを請求できます。
備考欄が自由に書けます。
一般住宅と長期優良住宅にした場合のおおよその差額を請求しましょう。
▼家作り計画書サービスはこちら▼
-

-
これからマイホーム計画をするあなたへ『家作り計画書』を作るメリット
続きを見る
まとめ:長期優良住宅はよく考えて建てましょう
長期優良住宅は厳しい認定基準を満たした住宅のことです。
たくさんの補助金・税金控除がある一方で、家の価格自体は高くなります。
予算がなければ建ちません。長期優良住宅にすることでいくら予算が上がるのかを聞くことからスタートしましょう。
以上、『【知りたい】長期優良住宅って結局何なの?性能基準や補助金、住宅ローン控除について解説』という記事でした。
-

-
これからマイホーム計画をするあなたへ『家作り計画書』を作るメリット
続きを見る
-

-
【家づくりを絶対節約!】Ryotaハウスツリー/比較で節約する情報まとめ
続きを見る
-

-
耐震等級3の地震に強い家を建ててわかった4つのこと『個人で備える』
続きを見る
-

-
新築の住宅ローン控除ってどのくらい?気になる控除額・適用条件について
続きを見る




